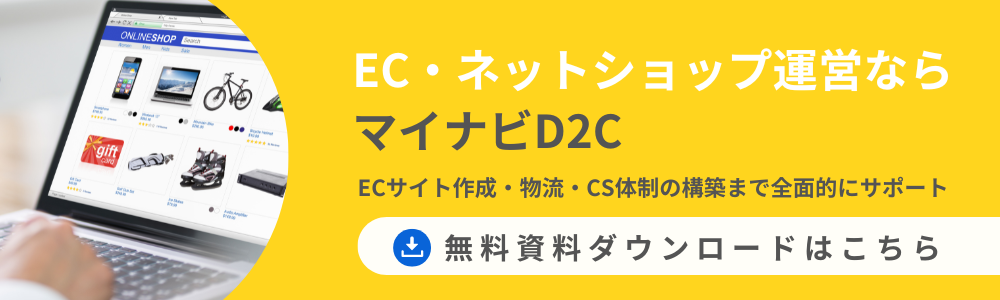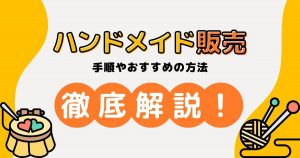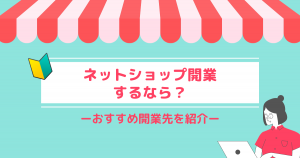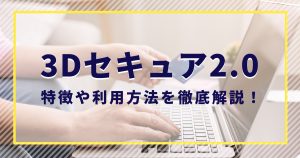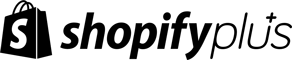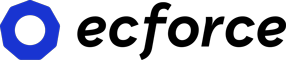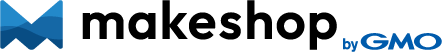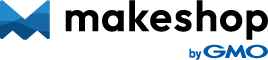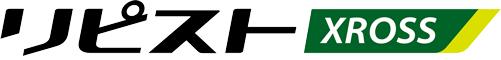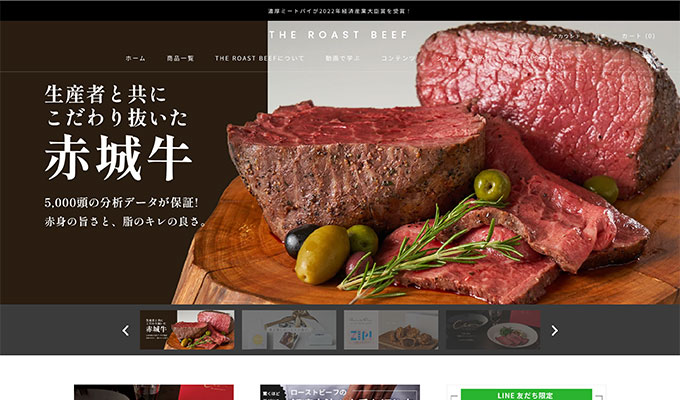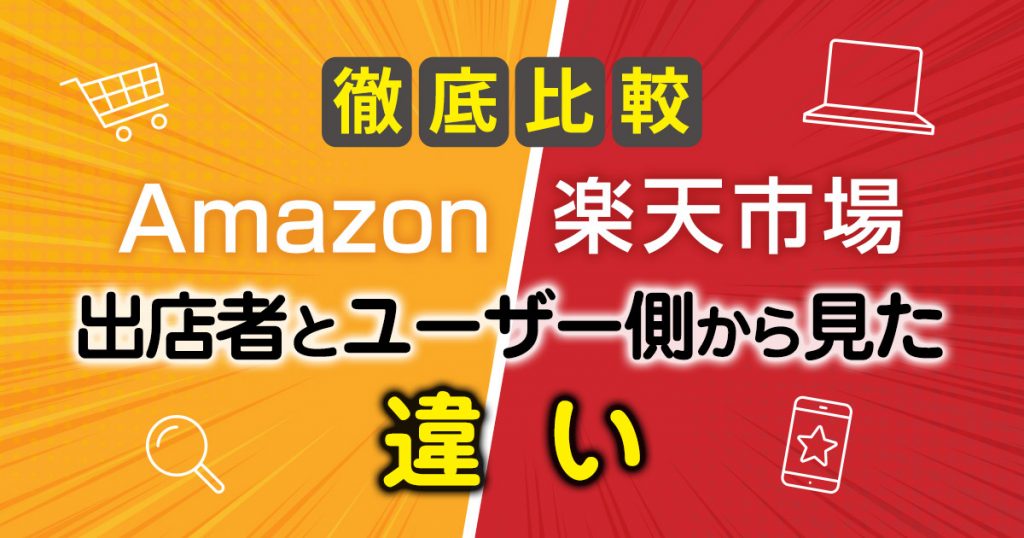ツール導入
JANコードとは?作成手順から仕組みや導入するメリット・デメリットを詳しく解説
商品を買う際にレジでバーコードを読み取りますが、このバーコードを「JANコード」と言います。
普段よく目にするものではあるものの、何のためにあるのか、意外と知らない人も多いのではないでしょうか?
JANコードの目的はレジ作業をスムーズにするだけでなく、さまざまな役割を果たしています。
以下のとおり、商品を販売する側にとっては非常にメリットが大きいものです。
<JANコードを導入するメリット>
<JANコードを導入するデメリット>
今回は、JANコードの仕組みや導入するメリット・デメリット、作成手順まで詳しく解説します。
これから物販ビジネスを始めようとしている人は、ぜひこの記事を読んで、JANコードの導入を検討してみてください。
- 更新:
- 2023年06月12日
COLUMN INDEX
- JANコードとは?
- JANコードをつける目的
- JANコードの体系
- 他のバーコードやQRコードとの違い
- JANコードを導入するメリット
- 業務効率化を促進できる
- ヒューマンエラーを防止できる
- データを蓄積できる
- 販路を拡大できる
- JANコードを導入するデメリット
- 初期費用がかかる
- 導入時に大きな手間がかかる
- マニュアルを作成・周知する必要がある
- JANコードを作成する手順
- ①GS1事業者コードの登録
- ②商品アイテムコードの設定
- ③チェックデジットの計算
- ④JANコードの印刷
- ⑤取引先へのJANコードの通知
- JANコードの作成にかかる費用
- JANコードに関するよくある質問
- JANコードとは?
- JANコードと他のバーコード、QRコードとの違いは?
- JANコードを導入するメリットは?
- JANコードを導入するデメリットはある?
- JANコードはどうやって作成できる?
- まとめ
- 参考サイト
JANコードとは?

JANコードとは、商品情報が設定されたバーコードのことです。
JANコードを商品にシールにして貼りつけることで、商品管理や在庫管理がスムーズに行えます。
バーコードには、販売した事業者や商品の情報が登録されており、世界共通の識別番号がついているのが特徴です。
JANコードのJANは「Japanese Article Number」の略で、国際的にはEANコード「European Article Number」あるいはGTIN-13、GTIN-8と呼ばれています。
セリフ「JANコードを設定すれば、商品管理や在庫管理の手間が大幅に削減されるでしょう。」
JANコードの使い方としては、例えば以下のようなものがあります。
<JANコードの使い方>
- ・POSシステムでの商品管理
- ・売上金管理
- ・在庫・仕入れ管理
- ・消費者の動向把握
このように、JANコードは商品の販売業務において幅広く使われる仕組みです。
ここでは、JANコードを使う目的やコードの体系、他のコードとの違いについて解説していきます。
JANコードをつける目的
JANコードをつけると、商品の情報を人間が読み取って管理する必要がないため、商品の認識、管理作業の効率が大幅に向上するメリットがあります。
商品管理や在庫管理、仕入れ管理の効率を向上したい場合には、JANコードの導入がおすすめです。
販売管理の効率向上のため、POSシステムを導入している企業も多いと思います。
「POSシステムだけでなく、JANコードも導入すれば、さらに販売管理や商品管理、仕入れ管理の効率が向上するでしょう。」
JANコードが商品についていれば、バーコードリーダーでJANコードを読み取るだけで瞬時に何の商品かをPOSシステムに入力できます。
人間が商品を判別して対応するレジのボタンを押す必要がなく、一瞬で商品を判別できるので作業時間を大幅に削減できるでしょう。
また、商品情報が登録されているので、商品がどれだけ売れたか、どれだけ残っているかという商品の在庫管理も容易です。
POSシステムだけの場合、商品管理の手間がかかることは変わりませんが、JANコードを導入すれば商品管理の効率が大幅にアップするでしょう。
JANコードの体系
JANコードの体系は、13桁の標準タイプと8桁の短縮タイプにわかれているのが特徴です。
ここでは、それぞれのコード体系を簡単にご紹介します。
■標準タイプ(13桁)
9桁目または7桁目までが「GS1事業者コード」で、次の3桁または5桁が「商品アイテムコード」、最後の1桁が「チェックデジット」です。
商品アイテムコードが「00001」~「99999」まで使えるので、より多くの商品を扱えます。
■短縮タイプ(8桁)
6桁目までが「GS1事業者コード」で、次の1桁が「商品アイテムコード」、最後の1桁が「チェックデジット」です。
商品アイテムコードが「001」~「999」までしか使えないので、あまり多くの商品を扱えません。
JANコードを商品管理に利用する場合は、コードの体系もおさえておくとよいでしょう。
他のバーコードやQRコードとの違い
バーコードとQRコードは見た目が大きく異なるうえに、用途も違います。
バーコードは商品の販売管理や在庫管理に使いますが、QRコードはWeb上の広告やURLの指定などに使うことが多いです。
また、JANコード以外にも以下のようなコードが存在するので、違いを確認しておきましょう。
■ITFコード
JIS規格に準拠したコードで、国内外で利用できます。
■CODE39
JIS規格に準拠したコードで、工業用のコードとして利用されます。
数字以外にも、アルファベットや記号をコードに使うことが可能です。
■CODE128
JIS規格に準拠したコードで、CODE39と同じようにさまざまな文字の種類を利用できます。
■NW-7
JIS規格に準拠したコードでさまざまな文字の種類を利用でき、幅広い業界で使われています。
JANコードを導入するメリット
JANコードを導入すると多くのメリットを得られるので、商品の販売を行う事業者の人には導入を強くおすすめします。
JANコードを導入するメリットは、以下のとおりです。
<JANコードを導入するメリット>
ここでは、上記のメリットについて詳しく解説します。
業務効率化を促進できる
もっとも大きなメリットは、業務の効率化を促進できることです。
レジ作業では商品情報の読み取りが一瞬でできるため、レジ作業の大幅な時間短縮につながります。
セリフ「レジ作業が時間短縮されれば、顧客の待ち時間を減らせるので顧客満足度の向上につながるでしょう。」
また、コードで商品を認識して在庫数を瞬時に管理できるので、在庫管理作業や仕入れ管理作業もスムーズに進みます。
これらの業務が時間短縮されれば、人件費の削減にもつながるのです。
このように、販売業務における大半の業務は、JANコードによって大幅に効率化できることがわかります。
ヒューマンエラーを防止できる
JANコードがあれば商品をコードで自動的に認識できるので、ヒューマンエラーによる商品の認識間違いが起こらないメリットがあります。
店員が商品をひとつひとつ認識し、レジの該当ボタンを押すなどの手間がないので、レジの打ち間違いが起こりません。
JANコードがあればバーコードを読み取るだけでよいので、商品の判別内容を間違わないように気を付ける必要もないのです。
セリフ「レジの打ち間違いが多発すると顧客からのクレームにもつながるため、ヒューマンエラーを排除することでクレームが減るでしょう。」
商品のJANコードを登録する際に、人間が判断して打ち込む必要がありますが、それは最初だけです。
自動的に大量の商品情報を登録できるツールも利用できるので、積極的に利用してみてください。
ここまでご説明したとおり、販売管理作業や仕入れ作業などで商品の読み込みが自動化されるので、毎日の作業でヒューマンエラーが起こりにくくなります。
販売管理作業や棚卸作業、仕入れ管理作業などが大幅に効率化できるため、顧客満足度の向上や人員の削減、事業拡大にもつながるでしょう。
データを蓄積できる
商品をJANコードで管理すると、商品データを蓄積できます。
また、ポイントカードなどで顧客の年齢や性別なども管理できれば、顧客データの蓄積も可能です。
商品データや取引データ、顧客データなどが蓄積できれば、マーケティング活動に有効に活用できるメリットがあります。
例えば、在庫状況や売上状況のデータを管理し分析することで、商品がいつ、いくつ売れたのかなどがわかるのです。
セリフ「顧客データも分析に使えば、どの客層にどのような商品が売れているのかなども把握できます。」
このようにデータを分析に使えれば、客層ごとの売れ筋や、季節や天候によって商品の仕入れをどのようにコントロールすべきかなどがわかるでしょう。
このように商品データや顧客データ、売上データ、在庫状況のデータなどがあればさまざまな分析ができ、マーケティング活動に活用できます。
JANコード導入によりデータ分析ができるようになれば、売上アップにつなげることも可能です。
販路を拡大できる
JANコードによって商品管理することで、自社の店舗以外のECサイトや他店舗へ販路を拡大することも可能です。
ECサイトやデパートの物産展、道の駅などで自社の商品を販売する場合には、JANコードの表示が必要なので、JANコード対応していないと出店できません。
そこでJANコード対応をしておけば、自店舗以外に販路を拡大できます。
とくにECサイトで販売できれば、日本全国に新規顧客を大幅に増やせる可能性が高まるのです。
セリフ「このように、JANコード対応をすることで販路を拡大でき、売上アップにつながるでしょう。」
JANコードを導入するデメリット
JANコードを導入すると得られるのはメリットだけではなく、デメリットもあるため注意する必要があります。
JANコードを導入するデメリットは、以下のとおりです。
<JANコードを導入するデメリット>
ここでは、上記のデメリットについて解説します。
初期費用がかかる
JANコードを利用するためには、初期費用がかかります。
JANコード対応のレジ、ハンディーターミナル、タブレットなどの専用のハードウェアが必要です。
また、JANコードを取り扱うための在庫管理システムなど、ソフトウェアのライセンスを購入して、ハードウェアにインストールしなければなりません。
セリフ「さらに、バーコードシールをすべての商品に貼る必要もあるので、シール代金や貼りつける際の人件費もかかります。」
ハードウェアやソフトウェアの導入、商品へのシール貼りなどは、ひとつの店舗だけに対応すればよいわけではありません。
複数の店舗や物流拠点、倉庫、工場、営業所などがある場合は、すべての拠点に対応が必要です。
このように、JANコード導入時にはまとまった初期費用が必要なので、導入時には細かく費用を見積もっておくことをおすすめします。
導入時に大きな手間がかかる
上記でご説明したハードウェアやソフトウェア、商品へのシール貼り対応などはコストがかかるだけでなく、当然手間もかかります。
まず、ハードウェアやソフトウェアの選定を行うことが必要です。
コストや業務との相性、使い勝手、性能などを考慮して選定しなければなりません。
ハードやソフトを導入しただけではすぐに使い始められず、既存システムをJANコードに対応したシステムに再構築する手間も生じます。
セリフ「もちろん、すべての商品にシールを貼るのは、言うまでもなく大きな手間がかかりますよ。」
このように、JANコードの対応はハードやソフトだけでなく、すべての商品にシール貼り替えが必要なので、導入時の手間は非常に大きくなります。
店舗や営業所、倉庫、工場などが多い場合は、それだけ手間も増えるのです。
そのため、JANコードを導入する際には、店舗を臨時休業してハードやソフトの導入対応やシール貼り対応を行う必要があるでしょう。
臨時休業による売上減少や、臨時作業の人件費の確保も見込んでおく必要があります。
マニュアルを作成・周知する必要がある
JANコード対応を行うと、従業員の商品管理作業や仕入れ作業などが大幅に変更されます。
新しい商品を仕入れた場合のJANコード登録作業が追加され、商品のレジ打ち時の作業、仕入れや在庫管理時の作業などがすべて変更されるのです。
そのため、商品管理者や販売員向けの作業マニュアルを新たに作成し、周知する必要があります。
セリフ「作業マニュアルは一度作って配布するだけではなく、必ず実際に作業してみて問題点を確認しましょう。」
実際に運用すると、レジを打った後に取り消しする方法がわからない、登録した商品の帳票出力はどうすればよいのかなど不明点が出てきます。
これらの不明点やマニュアルの不備を確認し、修正して周知しましょう。
また、マニュアル類は運用を続けていくと運用フローの変更や不具合が必ず出てきます。
定期的にマニュアルを見直していく必要もあるでしょう。
JANコードを作成する手順
JANコードを作成する手順について以下のとおりまとめました。
<JANコードを作成する手順>
JANコード対応を始める際に、ぜひ参考にしてみてください。
①GS1事業者コードの登録
まずは、「GS1事業者コード」を登録します。
コードは国別コードから始まり、最初の二桁が「45」か「49」で始まるのが日本のコードです。
GS1 Japan「一般財団法人流通システム開発センター」にインターネットか書面で申請すれば、自社の事業者コードを登録できます。
インターネットでの申請の手続きは、以下のとおりです。
<GS1事業者コードの登録申請手続き>
- ・GS1 Japan「一般財団法人流通システム開発センター」に新規登録する
- ・申請フォームから必要事項を入力して申請する
- ・登録申請料を指定の方法で支払う
- ・約7営業日後に「GS1事業者コード登録通知書」が届く
登録申請は非常に簡単なので、公式サイトも確認して申請してみてください。
②商品アイテムコードの設定
次に、商品アイテムコードを設定します。
商品アイテムコードは、同じ商品の色や種類、内容量ごとに設定が必要なのでご注意ください。
GS1事業者コードが9桁だと、商品アイテムコードに使えるのは3桁で、「001」~「999」まで使用できます。
GS1事業者コードが7桁だと、商品アイテムコードに使えるのは5桁で、「00001」~「99999」まで使用することが可能です。
セリフ「後者の方がたくさんの商品アイテムコードを使えます。」
商品コードの割り当ては今後商品が増えることを考えて、拡張性を持って設定しましょう。
商品の種類や部門ごとに数字を割り当てておくよりも、「00001」から順番に割り振っておくのがよい方法です。
コードを割り当てる際には、効率のよい割り当て方法をGS1 Japan「一般財団法人流通システム開発センター」の記事やインターネットなどで調べてみてください。
③チェックデジットの計算
チェックデジットはJANコードの末尾1桁の数字で、コードを特定の方法で計算して算出するものです。
チェックデジットは、JANコードを読み取る際に誤りがないか検証するために使います。
チェックデジットの計算方法はGS1 Japanが定めており、公式サイトに計算フォームが記載されているので簡単に算出することが可能です。
なお、計算フォームは13桁の標準タイプのコードと8桁の短縮タイプのコード、どちらにも対応しています。
セリフ「それぞれの商品アイテムコードのチェックデジットを計算しすることで、JANコードが決まるのです。」
④JANコードの印刷
JANコードが決まったらシールに印刷し、JANシンボルとしてすべての商品に貼れるよう、商品数分を用意します。
通常の場合、印刷は印刷会社に依頼することが多いです。
商品ごとのJANコードとそれぞれの商品の数量を確認し、印刷会社に依頼しましょう。
セリフ「もちろん自社でプリンタを用意して、JANシンボルを印刷することも可能です。」
ただし、JANシンボルはJIS規格で定められたサイズや品質基準を満たさなければならず、自社で印刷すると基準を満たせず、使えないこともあり得ます。
そのため、JIS規格を満たすJANシンボルを印刷できる印刷会社に依頼する方が、コストはかかりますが効率良く作成できるでしょう。
また、チェックデジットの計算も必要ですが、計算から印刷まで印刷会社が対応してくれる場合もあります。
セリフ「印刷だけでなく、チェックデジットの計算にも対応してくれる印刷会社を選ぶとよいでしょう。」
JANコード印刷に対応した印刷会社は、GS1 Japanの公式サイトに掲載されているので、調べてみてください。
JANコードは、商品の販売を行うなら継続して作り続ける必要があるものです。
そのため、信頼できる印刷会社を選び、長期的に契約しましょう。
⑤取引先へのJANコードの通知
JANコードは自社での販売時や在庫管理時に使うだけでなく、取引先が商品を指定する際などにも使います。
商品カタログに商品の詳細とともにJANコードを記載し、取引先に渡すとよいでしょう。
取引先側も自社のシステムに商品のJANコードを登録でき、在庫管理などに活用できます。
JANコードを使うのは自社だけではなく、取引先での在庫管理や検品管理などにも使うので、必ず周知しましょう。
JANコードの作成にかかる費用
JANコードの作成にかかる費用は、大きく以下のようにわかれます。
<JANコードの作成にかかる費用>
- ・GS1事業者コードの新規登録申請料
- ・JANコード設定時の人件費
- ・JANシンボルの印刷費用
GS1事業者コードの新規登録申請料は、企業の年間売上高が3年払いか、1年払いかによって以下のように変わります。
【GS1事業者コードの新規登録申請料の分類(3年払い)】
【GS1事業者コードの新規登録申請料の分類(1年払い)】
JANコード設定時の人件費や印刷費用は、商品量や印刷会社の工賃などによって異なるので、事前に見積もってみてください。
JANコードに関するよくある質問
JANコードに関するよくある質問についてまとめました。
JANコードの導入を検討する場合に、ぜひ参考にしてみてください。
<JANコードに関するよくある質問>
JANコードとは?
JANコードはお店で売っている商品についているバーコードで、販売した事業者や商品の情報が登録されており、世界共通の識別番号がついています。
JANコードについての詳細はこちら『JANコードとは?』をご覧ください。
JANコードと他のバーコード、QRコードとの違いは?
JANコード以外にもITFコード、CODE39、CODE128、NW-7などのコードがあり、用途やコード体系などがそれぞれ異なります。
JANコードと他のバーコード、QRコードとの違いについての詳細は、こちら『他のバーコードやQRコードとの違い』をご覧ください。
JANコードを導入するメリットは?
JANコードを導入するメリットは、以下のとおりです。
<JANコードを導入するメリット>
JANコードを導入するメリットについての詳細は、こちら『JANコードを導入するメリット』をご覧ください。
JANコードを導入するデメリットはある?
JANコードを導入するデメリットは、以下のとおりです。
<JANコードを導入するデメリット>
JANコードを導入するデメリットについての詳細は、こちら『JANコードを導入するデメリット』をご覧ください。
JANコードはどうやって作成できる?
JANコードを作成する手順は、以下のとおりです。
<JANコードを作成する手順>
JANコードを作成する手順についての詳細は、こちら『JANコードを作成する手順』をご覧ください。
まとめ
今回は、JANコードの仕組みや導入するメリット・デメリット、作成手順まで詳しく解説しました。
JANコードとは、お店で売っている商品についているバーコードで、販売した事業者や商品の情報が登録されており、世界共通の識別番号がついています。
JANコードは登録する手間がかかるなどのデメリットもありますが、最初の手間さえ終えてしまえば商品管理の効率が大幅に向上するのです。
レジで商品を瞬時に認識できますし、商品の在庫管理や消費者の動向把握まで簡単にできます。
この記事でご紹介したJANコードの作成手順を参考にしていただき、商品管理の効率向上にお役立てくださいね。
参考サイト
人気記事
PICK UP
注目のキーワード
資料ダウンロード(無料)
CART MALL
対応カート・モール一覧
OUR SERVICE
サービス紹介
マイナビD2Cは、お客様のECサイト作成、物流・CS体制の構築に至るまでECに関わる全てをサポートする「総合EC支援サービス」です。
ECスペシャリストがお客様と伴走し、売れるECサイトに育てていきます。
-
ECサイト制作・運用
日本11位のドメインレートを持つマイナビD2CのECパートナーが徹底サポート。

-
マーケティング支援
データを活用し、売上最大化のためのアクションが途切れない活発なショップへ。

-
物流支援
物流システム(WMS)・発送業務を得意とする倉庫の選定など、安心・安全な物流フローを 構築。

-
DX支援
受発注管理や在庫管理、BI導入、業務改善など、デジタルの力で事業推進を図ります。

CLIENT WORKS
事例紹介
抱える課題が違えば、適切なソリューションはそれぞれ異なります。
多くの企業様と様々なメディアの成長を見守ってきたノウハウが、私達の財産です。
PICKUP COLUMN
おすすめ記事
CONTACT
資料請求・お問い合わせ
デジタルソリューションを導入したいが何から始めたら良いか分からない。
既存のメディアをもっと有効に活用し、成長させたい。
自社にリソースがなく、導入から運用までアウトソーシングしたい。
上記のようなお悩みレベルのご相談がある企業様、課題を探すところから
サポートが必要な企業様もぜひお気軽にお問い合わせください。